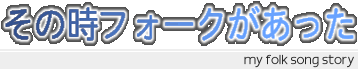 その7 .......
2004年5月初旬、ふとしたきっかけから、長い間敬愛していたフォーク歌手、及川恒平さんの北海道初ソロライブを主催することになった。このあたりの経緯はとても説明しにくい。正直な実感として、こうなることが運命だったような気がしないでもない。そうでも思わなければ、興行経験皆無の素人が、プロ歌手のコンサート企画など、とても出来るものではない。 恒平さんの勧めもあり、運営に協力してくれそうな音楽仲間に何人か声をかけた。企画に至る経緯は恒平さんの掲示板でも広く公開されていたので、メールによる見知らぬ方からの援助の申し出も相次いだ。妻や息子の全面協力もとりつけた。
相前後して、自宅2階の仕事場の一隅にあったライブコーナーに木製のベンチを増設した。コンサートの企画会議にあわせ、仲間内でミニライブをやろう、という目論見からである。「この種の企画は、まず主催者自身が楽しむ、という視点が大切です」と、恒平さんからの助言もあった。
 自宅2階一隅にしつらえた常設ミニライブコーナー/2004.12
こうしてこのライブコーナーを拠点に、主として企画会議終了後に時間のある人だけ残って、よくフォークセッションを開いた。僕を含め、メンバーにギターの出来る人、歌える人がかなりいたので、演奏者には事欠かない。
特に「達者でナ」は、小学生のころ、親に隠れて(母親は演歌を歌うことを僕に禁じた)学校の行き帰りによく歌った記憶がある思い出の曲だ。高音部のメロディがとても美しく、歌のテーマも愛しさと切なさに満ちていて、及川恒平さんの歌にどこか相通ずるものがあると僕は考えている。
6月になり、会場に決まった札幌時計台に妻と二人で、あるいは独りで、幾度か打合せや調査のために通った。 ある日の夕暮れ、メインポスターに使うための写真を時計台周囲をゆっくり周りながら撮影していたとき、うす青く暮れようとしている空と時計台の塔、そして回りを囲む木々の隙間から、何かが僕の上にはらはらと落ちてきた。 それは幾篇かの言霊と、それを飾る旋律だった。歌である。 僕は天が与えてくれたに違いないその言霊と旋律とを、大切に拾い集めた。ここでは、メモなどの形ある行為は、かえって思考のさまたげになる。ただ目を閉じて、イメージを丹念に頭の中でなぞるだけでいい。
家に帰り、デジタルカメラの画像を整理しながら、拾い集めた言霊と旋律を少しずつまとめていった。それから1週間ほどのうち、全部で3つの曲が形になった。そのうちのひとつ、「街染まる」は、一部をのちにポスターの詩篇としても使うことになる。 僕は何か事を興すとき、必ず強いイメージを自分の中に作り上げる。そのイメージが鮮明であればあるほど、事はうまく運ぶ可能性が高い。僕はこの歌を自ら「及川恒平時計台コンサート・イメージソング」と名づけ、このイメージに向かって突き進むことで、自分を鼓舞しようとした。
あくまで「自己完結タイプ」の歌だったが、これまたひょんなきっかけで、コンサートのリハーサル時に、ご本人の及川恒平さんの目の前で歌う、という幸運に恵まれた。しかも、二度まで…。
7月末、地元新聞に「時計台虹雪コンサート、市民バンド参加者募集」という記事が載った。札幌オリンピックのテーマソング、「虹と雪のバラード」の作詞者である詩人の河邨文一郎さんが亡くなったのを機に、「虹と雪のバラード」の詩碑を札幌市内に建てようという運動の一環らしい。 出演はアマチュア10組限定で、オーディションはない。「虹と雪のバラード」を歌うのは必須だが、一組10分の持ち時間の中で、もう1曲歌えるという。会場となる時計台ホールの音響設備や照明の様子、準備の感じなどを肌で感じ取る願ってもない機会と思い、迷わずエントリーした。
当初は僕一人で参加予定だったが、念のためスタッフの一人に声をかけると、この際バンドを組んで出ませんか、との積極的な反応。もう一人の女性スタッフを半ば強引に説得し、3人で急きょユニットを組んで出演することになった。
自由曲は紆余曲折のすえ、及川恒平さん作詞作曲の「夏・二人で」に落ち着いた。男女が完全二重唱で歌う、流れるようなメロディが特徴の爽やかな曲である。虹雪コンサートの実施期日が8月31日、去りゆく夏を惜しむのにもふさわしかった。
数日前から体調を整え、コンサート当日の会場入りの直前には、道端に停めた車の中で一人最後のボイストレーニングに励む。と言っても、音楽の専門教育など何も受けていない我が身、これまでのように、ただ闇雲にその日歌う曲を何度も歌うだけなのだった。
これといったミスもなく、1曲目を終える。実は歌いながら、注意深く会場の様子をうかがっていた。バンド演奏の場合、自分の歌、自分のギター、他のメンバーの楽器と歌、そして会場の反応と、およそ5つくらいの要素に同時に気を配り、バランスを保っていかなくてはならない。とても神経を使うのである。
2曲目の合間に、しばしの語り(MC)を入れる。フォークにMCは欠かせない。グループ結成の由来から話題を10月のコンサートにもってゆき、しっかりアピール。「それではその及川恒平さんが作詩作曲した曲を次に歌います」と、「夏・二人で」に入っていった。
会場にいた妻と息子の終演後の反応も上々だった。「次回もぜひ出てください」と、コンサート責任者の方からお誘いを受けるおまけまでついた。
9月に入って、チケットの販売にムチが入った。興行的な意味からも、またできるだけ多くの人に及川恒平さんの歌を聴いていただく主旨からも、ある一定の観客数は確保したかった。 ステージとギターが常設されていて、客が自由に歌っていいという、粋な計らいのフォーク居酒屋をネット検索で市内に見つけ、掲示板での広報をマスターにお願いすると、心良く応じてくださった。お礼とさらなる広報をかね、スタッフのギタリストと二人で店に出向いた。
この店のマスターが、某スーパーを50歳目前に中途退職し、かねてからの趣味だったフォークを取り入れて店を開業したという、波乱の経歴を持つ方だった。奥様(ママさん)もそれを暖かく手助けしていて、同様な経緯でデザイン事業を興した数十年前の自分の姿と、どこか重なって身につまされた。
「今度は菊地さんたちが歌ってくださいよ」と、歌い終ったマスターが言う。我に帰った僕は、(ちょっとやりにくいな…)と、正直思った。どんなライブでも、上手い人が歌ったあとはやりにくい。しかし、(今夜は及川恒平さんのPRに来たんだ…)と自分に言い聞かせ、ステージに上った。
調子に乗って、「面影橋から」を続けて歌った。この歌はカラオケにも入っている恒平さんの代表曲だ。人前で歌うのはこれが初めてだったが、この夜の声はよく伸びた。リードギターの方との音合わせは不十分だったが、そのせいでバランスをほとんど無視し、ソロの気分で歌ったことが逆に幸いした感じだ。そしておそらく、マスターが最初に作った世界が、僕のキモチのなかでいいほうに作用していた。
10月19日に第2回の「時計台虹雪コンサート」が実施された。打ち明けると、さすがの出たがりの僕でも、度重なるライブとコンサート準備の雑用に謀殺され、このコンサートに出る意欲は当初なかった。「恒平さんのコンサートのPR」そして、「時計台ホールの会場調査」という本来の目的も、最初のコンサート参加で、ほぼ達成している。 僕の持論として、「楽しいことは1回だけ」というものがある。子供たちが幼かった頃にも、そのことは充分言い聞かせて育ててきた。準備万端整えたイベントの最初の楽しさは分かるとして、その楽しさを同じ条件下で、2度3度と保ち続けることがいかに難しいことであるか、幼い頃からそう豊かな生活を得る環境下にはなかった僕や妻には、そのことが身に染みて分かっていた。 楽しい出来事はただ1回だけだからこそ色あせず、心地よい思い出として末永く心に留まっていられる、それが弱者としての僕の人生訓だった。
しかし、それでも結局出たのは、他のメンバー二人の意見が、「出たい」という方向で一致していたからである。エントリーバンドに課せられるチケット代まで、二人は負担してくれると言う。(初回は全額僕が負担)日頃スタッフとして手弁当で気苦労をかけているメンバーのそこまでの申し出を、むげに却下することはとても出来なかった。自我を棚上げにし、義理を重んじたのである。
このときはMCを少なめにし、自由曲を2曲歌う予定だった。だが、1グループ10分以内という厳しい制約時間がある。課題曲も間奏を極力省き、それに合わせることにする。
そこで、「りんご撫づれば」を歌ってみた。恒平さん本人の曲でもあり、今度はメンバーからも異論は出ない。いったんはこれで決着しそうになったが、残念ながらこの曲はほとんどソロむきの曲である。曲が長い、ということも問題だった。
しかし、これまた結局は僕が折れた。リードボーカルの負担が大きいこの曲は、僕の出来不出来がバンド全体に大きく影響する。受け入れた以上、毎日何度も個人練習する羽目になったが、低音部と高音部のバランスの取り方が難しく、歌い終えるとかなりのエネルギーを使い果たし、ぐったりと疲れた。 コンサート全体の雰囲気としては、予想していた通り、初回の楽しさ、ワクワク感は望むべくもない。だが、これは我々の出来不出来とは無関係で、それが自然の摂理というものである。
予定通り、10月31日に「及川恒平時計台コンサート」は実施された。その全容はこのサイトにある「及川恒平札幌ライブProject」に詳しいので、詳細は省く。僕としては長年の夢とあこがれだった及川恒平さんのソロライブを無難に終えることが出来、主催者として、そして一ファンとして、とても喜んでいる。 恒平さんにも実に「気分よく」札幌ツアーを楽しんでいただけたようだ。そしてスタッフ3人で編成したPRバンド、「ジャングルジム」には、本番の時計台ホールの舞台で、あの「夏・二人で」を恒平さんと共演するという、おそらくこれから二度とないであろう貴重な経験まで与えていただいた。
打ち明けると、僕はこのコンサートの本番で泣いている。「夏・二人で」の共演が終ったあと、恒平さんが舞台を降りようとした僕を不意に呼び止め、お客様に紹介してくださった。僕はこのコンサートを主催はしたが、あくまで黒子である。スポットライトを浴びるのは主役の恒平さんだけでいい、そう考えていた。
間近にいた恒平さんは、もちろん僕の涙に気づいたはずだったが、コンサートはまだ続いている。その舞台に悪い影響を与えてはならない…、そう判断した僕は舞台の陰にさりげなく回って自分の表情を悟られないようにした。
コンサートで最も記憶に残ったのは、実はリハーサルで最初に恒平さんが歌ってくださった、「さみだれ川」の歌声である。照明機材を2階ホールに運ぶ途中の暗い階段の途中で、僕はその歌を独り聴いた。
コンサートが終って1ヶ月近くが過ぎた。僕は溜っていた仕事や日常雑務、そして主催者としての残務整理などもあって、日々忙しさに追われていた。 11月末、恒平さんからコンサートに関わった人たちに、ある「贈り物」が届いた。その「贈り物」とは実は歌である。恒平さんが札幌で過ごした数日間の思いや気持ちを率直にまとめたものだった。その歌には、もしかすると僕にしか理解出来ないかもしれない恒平さんの優しい気遣いや思いやりがたくさん詰まっていて、僕や妻は再び熱い嬉し涙に暮れた。 その日、またしても一篇の詩が僕の中に舞い降りてきた。この半年間に恒平さんからいただいた数々の恩恵に対し、僕は何かしらの「お礼」をしたいとずっと考えていた。コンサートに向かって僕を内側から支え、励ましたのが僕自身の作った歌であったので、その「お礼」も、やはり歌が最も相応しかった。
コンサートの終った頃から、タイトルだけは「ありがとう」にしようとぼんやり考えていた。感謝の気持ちを表すのに、これ以上シンプルで気持ちが率直に伝わる言葉は見つからない。メールや掲示板で、恒平さん自身がしばしば用いる言葉でもある。 家に戻って言葉と旋律を整理し、少し歌詞の順序を入れ替えたり、部分的に変更したりした。ちょうどその頃、ミキサーとMDコンポを購入し、簡単な多重録音が出来る環境を自宅に整えたばかりで、コンサートのスタッフでもあった息子に手伝わせ、自宅内スタジオで一気に録音した。
恒平さんに関する小さな仕掛けと想いがあちこちにちりばめられていて、またしても「自己満足完結型」の曲と言える。「あれ?これはなんだろう…」と思う個所がもしあったら、きっとそれはその「仕掛け」の部分だ。しかし、そんな経緯で作られたにも関わらず、聴いてもらった家族や友人間での評判はとても良かった。 この曲は、公開前に細かいいきさつを添えて恒平さん本人にも聴いていただいた。恒平さんの感想はここには書かないが、この曲を贈ったことで、僕の「及川恒平時計台コンサート・主催者」としての仕事は、真に終りを告げたような気がいましている。 |
 達者でナ /2004
達者でナ /2004
 街染まる /2004
街染まる /2004
