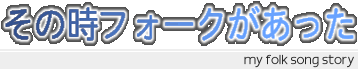 その6 .......
人生勝負をかけた脱サラ後の数年間、ギターや歌からはしばし遠ざかった。「苦しいときこそフォーク」のはずだったが、「苦しさを自覚する暇がないほどの緊張感と忙しさ」には、さすがにフォークが入り込む隙間もなかったとみえる。 70年代後半から、増え続ける楽譜の山を整理整頓する画期的手段として、「B6サイズカード」による楽譜カードを使いはじめた。「整理学」という言葉が世に認知され始めた時期と一致する。サイズや体裁もまちまちだったそれまでのノート式の楽譜が、1枚ずつきれいにカードに書き写され、ジャンル別に整理整頓された。 最近ではこのデータをもとにし、さらに近代的で場所をとらないパソコンを使った電子楽譜にまで発展させたが、当時作った手書きの楽譜カードは、いまでもかなりの数が手元に残っている。年代を調べてみると、オリジナル曲はもちろん、一般曲にも80年代に作ったカードは極めて少ない。趣味としての音楽活動が停滞していた証拠である。
1986年冬、上の娘が通っている小学校でサケ学習を通じた国際交流の行事があり、カナダから40人の子供たちと数人の引率の大人たちが大挙やってくることになった。宿泊はすべて地域のホームスティが条件である。数年前からラジオで英会話を独学して準備していた僕は、待ちわびていたこのホームスティを受け入れた。 この日にふさわしい曲を数曲ピックアップし、簡単な英訳もつけて備えた。日本情緒の感じられる曲でギターで歌えるものというと、これまたそう候補は多くない。苦心のすえ、次の3曲に絞りこんだ。
「竹田の子守り歌」〜京都府民謡 食事とデザートが無事済んでみながリラックスした頃を見計らい、仕事部屋の奥からギターを持ち出してきた。場がたちまち拍手に包まれる。
「カナダのお客様のために、親愛の情をこめて日本の歌を歌います」とかなんとか言って歌い始めた。「竹田の子守り歌」はキーを高めのCにしたが、練習のかいあってこの夜の声はよく伸びた。カナダのお母さんたちは、じっと歌声に聞き入っている。 「あなたはとても美しい声をしている」
涙をいっぱいにためたまま、客の一人のルーツ夫人が言った。「ちょっと悲しい曲でした」と、僕は自分の涙の言い訳をするように答えた。
予定していた残りの2曲のうち、「赤い花白い花」を家族全員で歌ってファミリーライブはお開きとなった。
独立して事業を始めて数年の間に、3度のコンサートに行った。井上陽水、谷山浩子、堀内孝雄の順で、このうち堀内孝雄は知人が行けなくなったチケットをもらっただけなので、積極的に行ったのは井上陽水と谷山浩子だけということになる。 打ち明けると、僕はあまりプロ歌手のコンサートには行かない。フォーク系でも実際に観に行ったのは数えるほどで、学生時代に行った吉田拓郎、社会人になって行った泉谷しげる、銀河鉄道、たったこれだけだ。 おそらく僕は、プロのコンサートに足しげく通うより、自分や仲間と歌って楽しむことをより好むタイプなのだ。
6度の中の貴重な一人、谷山浩子は特に脱サラ以後によく聴いた。僕の仕事は自宅を拠点とした建築デザインの分野だったので、製作作業は深夜に及ぶことが多く、BGM代わりにラジオは欠かせなかった。よく聴いていた「オールナイトニッポン」という深夜ラジオ番組で、確か木曜明け方3時から5時までの担当が谷山浩子で、透明感のある歌声がとても好きだった。当時の放送のテープのいくつかが、まだ手元に残っている。
この歌を知ってから、いつか誰かの結婚披露宴でぜひ歌いたいと思った。ギターで歌えて、しかも愛の原点ともいえる強いメッセージを持つこれ以上結婚披露宴にふさわしい歌は、いまのところ見当たらない。しかし、どういうわけか、いまだにその機会が訪れない。
ひょんなきっかけで、1990年春から地域のサッカー少年団のコーチを始めた。僕はサッカーの楽しさ、教えることの面白さにとりつかれ、のめりこんだ。サッカーは趣味としての音楽活動から遠ざかる、さらなる理由となったと思う。 しかし、全く歌わなかったわけではない。仕事部屋の片隅にはいつもギターが置いてあり、気がむくとケースを開けて弾き、古い歌詞カードを引っ張りだしては、好きな曲を歌っていた。 日々の手入れを怠らなかったので、ギターはいつも新品のように輝いていた。しかし、「毎日弾くとギターは喜んでいい音を出してくれる」と、いつか誰かが言っていた。それが本当だとすると、週に1回、月に数回ほどのペースに落ち込んだ僕のギターは、たぶんあまりいい音で鳴ってはくれなかったはずだ。
1992年春、末の息子が小学校を卒業することになり、親子の卒業謝恩会がクラスで開催され、僕が参加した。時間の自由になる自宅での仕事だったので、事業運営にも余裕の出来たこの頃は、ホームスティでもサッカーコーチでも子供のクラス行事でも、その気さえあればいくらでも参加することが出来た。 「それでは最後に、菊地くんのお父さんに父母代表としてギターで1曲歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします」
思わず我が耳を疑った。全く寝耳に水だったからだ。事前に息子が先生に何か口走ったか、それとも、妻が何か聞いていて僕に伝えるのを忘れたか…。
いずれにしても、事前に電話があるなり、息子に「明日お父さんに歌ってもらうかもしれないよ」などと伝言があるのが普通だ。しかし、そんな一般常識がどうやらこの先生にはなかったらしい。 「それではご指名なので歌います。みなさん知っている曲ですので、ご一緒にどうぞ」
ギターの音やチューニングはまずまずだったが、ピックやカポはない。ベルトはついていたので立ったまま、(確かCで歌えたはず…)と、あいまいな記憶のままに「今日の日はさようなら」を歌い始めた。
アルペジオの前奏から入って歌い始めると、教室の後列に並んだお母さんたちが、すぐにあとに続いてくれた。子供たちの数人も一緒に歌いだし、教室の中はかっての歌声喫茶のようないい雰囲気になった。 この話には後日談がある。それから6年たったある土曜の午後、小学校のグランドで子供たちにサッカーを教えていた僕のそばに、二人の若い女性が近寄ってきた。
「菊地くんのお父さんですよね?」 二人の女性は、どこかで聞いたことのある名を名乗った。 「シンヤ君のお父さんでしょ?私たち、小学校で同じクラスでした」 言われてみて、ぼんやりとした記憶がよみがえった。そうだった、同じクラスにそんな名の女の子が確かにいた。でも、その子たちがなぜ…?僕はすっかり大人になって見違えるようになった彼女たちに、素朴な疑問を浴びせた。 「私たち、謝恩会で歌ってもらったあの歌のこと、よく覚えています」
グランドでサッカーを教えている姿をみて、すぐに分かった。懐かしくて思わず声をかけたと、彼女たちは続けた。僕はこれを聞いてとてもうれしくなった。
1999年春、僕は9年間続けた地域のサッカークラブの指導から完全引退した。理由はいろいろあるが、音楽とは無関係なので割愛する。 同じ年の5月、札幌すすき野にあるフォーク居酒屋で初めて歌った。ここはマスターが吉田拓郎の大ファンで、店の名前や調度品、BGMに至るまで、すべて拓郎で統一していた。店内にステージが常設されていて、拓郎の曲をマスターが毎晩ミニライブで聴かせてくれる。噂だと、拓郎の歌はすべて完璧に歌えるそうだ。拓郎の曲であれば客もどんどん歌ってよい、という粋な店だった。
かねてからこの店の存在は知っていたが、いくら出たがり目立ちたがりの僕でも、一人ではなかなか行く踏ん切りがつかない。人前で歌うことからしばし遠ざかっていたことも、気持ちを躊躇させた。 最初から歌うつもりでいたので、事前に次の3曲を準備し、楽譜も持って行った。
「どうしてこんなに悲しいんだろう」〜作詞作曲:吉田拓郎
9時を回るとマスターのミニライブが始まると聞いていたので、「前座」として、早めの8時頃に歌い始めた。客はたいしていなかったが、いざステージに上がると、久し振りの緊張感で喉がカラカラになっている自分に気づいた。
歌い進むうち、またしても涙が知らず知らず頬を伝った。このときは全く予期しない涙だったので、自分でも驚いた。若い頃には全くなかった「歌いながら涙が流れる」という現象が、年とともに頻発している。格好よく言うと、「年を経る毎に人生の愛おしさ、はかなさを思い知ってきたから」ということになる。しかし、ただ単に涙腺がゆるくなってきただけかもしれない。
この店には気がむくとたまに足を運ぶ。しかし、店が常連で混んでいると、僕は歌わずに聴き手に徹する。好きな店だけど、拓郎の歌以外は歌えないところに、ちょっと遠慮がある。もっとも、誰の歌でもOKとなってしまうと、店の存在価値そのものに、意味がなくなってしまうのかもしれない。
月日が流れ、1999年12月に僕たち一家は札幌郊外に戸建住宅を建て、引越した。サッカーはテレビ観戦だけとなり、週に3度の練習や日曜毎の試合指導からは完全に解放された。マンション住まいに比べて家は格段に広くなり、しかも周りには1軒の家もない「都会の中のオアシス」のような環境である。 いわば、「長い時間」「広い場所」「静かで気ままな環境」という夢のような3つの要素を一度に手に入れたようなもので、家が出来た当初は趣味と実益を兼ねた家具作りや庭作りの作業に謀殺される毎日だったが、数年を経るとやがてそれも落ち着いた。すると人間不思議なもので、眠っていた音楽の虫、ギターの虫がうずうずと騒ぎだしたのである。
先にもふれたが、古い楽譜や歌詞カードを引っぱりだし、少しずつパソコンに入力し始めたのもこの頃からだ。整理をするうち、むかし歌った懐かしい曲の記憶が次々とよみがえり、ついギターを引っぱりだしては歌い始める。住宅密集地にあったマンションと違って、夜中に歌っても、家族以外には一切迷惑はかからなかった。 「いつか趣味の音楽仲間を集めて、ミニライブでもやってみるか」 そんな途方もない僕の言葉に、妻もまんざらでもない様子だ。ほどなくしてその言葉は、あっさり実現することになった。
妻の職場仲間に、同年代で無類の音楽好きの女性がいて、子供も音楽大学に通わせている。ある雨の日の休日、いつもの調子でギター片手に歌っていると、その女性から電話があり、いまから我が家に遊びにやってくるという。
数えてみると、フォーク居酒屋で歌って以来、5年近く人前で歌う機会から遠ざかっている。いざ歌い出そうとすると、緊張で膝ががくがく震えた。しかも、このときは自分と聴き手との距離がわずか1メートルくらいで、あまりに近すぎた。 このときはパソコンの「電子譜面台」の検索機能を駆使し、その日の天候にあわせて雨にちなんだ3曲を、素早くその場で選んだ。
「雨が空から降れば」〜作詞:別役実、作曲:小室等
僕のライブでの定番とも言える1曲目は別にして、2曲目は三善英史が歌った演歌、3曲目はザ・ゴールデン・カップスが歌ったGSである。女性の趣味のひとつがカラオケだと事前に聞いていたので、選曲にも気配りしたつもりなのに、結果として最も受けたのは、やはり得意としている「雨が空から降れば」だった。
「5年ぶりのライブ」「聴き手との距離が異常に近い」「事前準備なしの突発ライブ」という悪条件の割には、自分としてはまずまず満足出来る演奏だった。
「せっかく招待されて、本心ではないお世辞を言わなくちゃいけない歌だったらどうしようかと思ってたけど、本当に上手でよかったわ」などと、女性は回りくどい感想を並べたが、かみ砕くとほめ言葉であることに違いはない。 |
 竹田の子守唄 /1986
竹田の子守唄 /1986
 河のほとりに /1988
河のほとりに /1988
