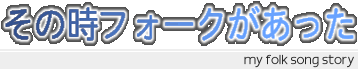 その5 .......
結婚を機に僕は設計課に配属変えとなり、図面台の前に一日中座る身となった。工事課よりも時間には幾分余裕が出来たが、HIRO以外に一緒に人前で歌えるメンバーは社内には見当たらず、何かの催し物で依頼があると、今度は一人で歌うしかなかった。 ギターは相変わらず上達しなかったが、伴奏はほどほどにしておき、もっぱら大きな声で勝負していた。僕にとっての最大の楽器は「声」そのものであり、ギターはあくまで声の引き立役に過ぎなかった。
一人で歌える歌にはそれなりに制限があり、当時よく歌っていたのは、ジュリーこと、沢田研二の歌である。フォークのジャンルではないこともあって、そう好きな歌い手ではなかったが、当時若い女性には絶大な人気を得ていた。あるとき会社の宴会で何気なくギター伴奏で「危険な二人」を歌ってみたら、これがバカ受けした。
当時、僕のことを社内では「…のジュリー」と呼ぶ人が幾人かいた。(…には会社名が入る)最近になってこのことをあるジュリーファンだった人に打ち明けたら、失笑を買ってしまったが、もちろん顔ではない。歌い方、特に高音部がちょっと本人に似ていたので、半ば揶揄する感じでそう呼ばれていただけのことだ。
フォーク系ではこの時期、井上陽水と及川恒平を多く歌っていた。ただし、及川恒平を歌うのはもっぱら妻の前だけで、会社で歌うときは井上陽水が多かった。この使い分けが非常に微妙なのだが、なぜそうなるかは、これまでの話からご理解いただけると思う。
結婚2年目にあたる1976年初頭に、四国高松の大きな工事現場への辞令が出た。神奈川の現場も大きかったが、立場はあくまで現場要員だった。今度は現場責任者という重い立場である。しかも発注は文部省直轄、つまりは国が相手なのだった。 会社始まって以来の大事なクライアントだったので、本社の設計要員で、ある程度工事の知識もある僕が狩り出されたらしい。
工事は夏をまたいで行われたので、北国育ちの僕には四国の酷暑が堪えた。初対面の下請け業者とはソリが合わず、現場の工期は遅れに遅れた。高松まで同行した妻は折悪しく身重で、初めて東京を遠く離れて暮す不安も重なり、いわゆる「マタニティブルー」状態に陥った。まさに八方塞がりである。
この「仕事上の重大な責任」と、「初めて父親となる責任」とは、僕を大きなストレスへと苛んだ。しかし、よく考えてみると、父親になる責任があったからこそ、難しい現場も助手なしの一人で何とか乗り切れたのかもしれない。
向い風 1976.5 作詞/作曲:菊地友則
ふるさとに似た 山に向かって 僕はペダル踏む フィーンフィーン フィーンフィーン
ふるさとに似た 山に向かって 僕はペダル踏む フィーンフィーン フィーンフィーン
やさしい春の 陽射しを浴び 短い影を追って
フィーンフィーン フィーンフィーン…
いろいろと雑多な物を背負いつつも、懸命に前に進んでいこうとしている若い僕の、人生に対する気負い、迷い、不安、そのあたりを感じ取っていただけるだろうか。 幾多の困難を乗り越え、現場はおよそ1年がかりで無事完成した。この曲が大きな心の支えになってくれたことは間違いない。苦しいときにこそ自分を励まし、救ってくれる。やはりこれが僕にとってのフォークだった。
高松の現場が終ると僕はすぐに本社に戻され、開発設計関係の部署に配属になった。 翌年の正月に札幌の実家に帰省したが、この時妻は同行していない。10月末に生まれたばかりの娘にとって、長距離の移動と北の寒さは過酷すぎると判断したからで、それなら家族で正月を過ごせばよさそうなものだったが、それでは実家に義理を欠くと、妻が僕だけに帰省を勧めたのだ。 顔を見せるだけなので、飛行機の空いている元旦に移動し、確か2泊だけして戻ってきたはずだ。独身気分で暇を持て余していた2日目の昼、学生時代に寮の同室だった先輩から、いきなり実家に電話があった。 「今夜、Mのところで一杯飲まないか。アイツ、結婚したばかりだから、おしかけてみようぜ」
雪の中、先輩が住む札幌市内の新婚家庭に、ノコノコ出掛けた。ドアを開けると、学生時代に顔見知りの懐かしい顔がいくつも並んでいて、よく見るとM先輩の奥さんも、1年上の同じ大学の先輩だった。 「菊地、お前まだフォークをやっているのか?もしやってるなら、俺たちのために何かいっちょう歌ってくれよ」 そういって奥からギターをゴソゴソ持ち出してくる。どこかであったような展開だったが、もちろん僕が断るはずがない。ギターを受取ってしばし考え、新婚の先輩を祝う意味で、小椋佳の「シクラメンのかほり」を静かに歌い始めた。 「おい、こっちにきて一緒に聴けよ、めったに聴けないいいものなんだから」
イントロのギターの部分が始まると、M先輩は台所にいた奥さんの手をひいて居間に連れてきた。「シクラメンのかほり」は、布施明の歌で有名だが、僕がいつも歌っているのは、小椋佳バージョンだ。歌詞は同じだが、メロディとリズムが微妙に違う。そして作詞作曲が本人である小椋佳バージョンが、「フォーク」だと僕は思っていた。 「相変わらずいい声だな。こいつは俺よりずっと後からギターを始めたのに、あっと言う間に追い抜きやがったんだ」 歌い終ると、M先輩と奥さんは大変喜んでくれた。何かと世話になった先輩への、これ以上ない僕からの結婚祝いだった。
上の娘に続いて1年半後に、息子が生まれた。僕たち夫婦はたちまち忙しく子育てに追われる身となったが、そんな中でも、フォークは常に身近にあった。 この頃よく聴いていたのが、イルカと及川恒平だった。上の娘は音感が鋭く、イルカや及川恒平のアルバムをかけてやると、どんなに愚図っていてもたいていは機嫌がよくなった。レコードに合わせて娘が楽しそうに手を降り、リズムをとっている当時の8ミリ映像が、家族の大切な記録として残っている。
「忘れたお話」のアルバムを新入社員のときに渋谷で偶然見つけて以来、及川恒平のアルバムは欠かさず買っていた。買い落としがあるといけないので、近所のレコード店に行き、「及川恒平のアルバムが発売されたら、必ず買うのでとっておいて欲しい」と強引に頼んだら、快く承知してくれた。以降、買い落としの不安からは解放された。
及川恒平の歌で当時僕が好んで歌っていたのが、「おやすみなさい」や「僕のそばにいなさい」、そして「懐かしい暮らし」だった。この3曲はセットで何度も何度も歌った記憶がある。3曲続けると、ある男女の愛のストーリーになるところがミソだった。
「おやすみなさい」は愛が成就する歌で、優しいメロディラインがとても好きだった。「階段を登り詰めた処にある…」の出だしが、新婚時代に借りていたアパートによく似ていて、歌の世界を自分と妻とに重ね合わせながら、いつも気分よく歌っていた。
話しが少し戻るが、最初の息子が生まれたとき、名前の第一候補に「恒平」が挙がった。「恒」はヒサシイに通じ、とわに続くもの、そして「平」はまっすぐな広がりを感じた。僕の好きな宇宙的イメージにもぴったりはまる。ファンが高じて我が子に同じ名をつけてしまうというありがちなパターンだったが、妻にも異存はなかった。
1978年、学生時代に寮で4年間同室だったSという男が結婚することになり、名古屋での披露宴に招待された。彼とは学部も同じ機械で、札幌の実家にも数回泊まったことがあり、身内のような親しいつきあいをしていた。 現役で大学に入ってきたSはひとつ年下だったが、風貌が僕にとてもよく似ており、一緒に酒を飲みに行くと、よく本当の兄弟と間違われたものだ。 「ぜひ1曲歌ってくれ」
電話でSは当然のようにそう頼んでくる。僕も快く応じたが、問題は何を歌うかだった。
披露宴の当日、カラオケやピアノ伴奏はいらない、と事前に言ってあったので、短い祝いの言葉のあと、いきなり歌い始めた。キーのズレが気になったが、歌ってみるとぴったり合っていた。歌う前にメロディを頭の中で何度もなぞっていたことと、最も高い音が出だしにくる、という曲の特徴にも救われた。朗々としたオペラのような曲調なので、何も伴奏がないこともそう大きなハンデにはならなかった。 「ありがとう、いい歌だった。俺もSや君と同じ大学出身だ。同窓として誇らしかったぞ」 Sの上司だったのかもしれない。彼の言葉に、僕は自分の歌への熱い賛辞を感じた。
1980年春、会社の常務に呼ばれ、プロの歌手の前座で歌うよう、不意に申し渡された。予期せぬ「業務命令」に、僕はうろたえた。従業員が300人弱の会社だったので、僕がギターやフォークで鳴らしていることは、社長を始めとする役員にまで知れ渡っている。それにしても、プロの前座はないだろう…。 聞けば、ある地方の有力な下請け業者の社長の息子が、プロ歌手として近々デビューするという。会社にとって大切な業者なので、出来るだけの応援をしたい。デビュー前の顔見せでやる東京でのライブの前座で、我が社の社員を二人歌わせることになった。そのトップバッターが君だ…。 重々しくそう告げる常務の話を聞いて、軽いめまいを感じた。その歌手は自分で曲を作る「シンガーソングライター」で、当時フォークという言葉は次第に一時の勢いを失いつつあり、それに変わるのがこのシンガーソングライターという耳ざわりのいい言葉だった。 演歌歌手ではないので、僕のやってきたフォークと大きな隔たりはない。しかし、いずれにしても、プロの前座などやる気はなかった。しかし、話の成りゆきから言って、その場で「出来ません」「やれません」では、どうも通りそうにない。
自分の歌がそれなりに受け、感動してくれる人がいるのは分かっていた。しかし、あくまでそれは素人レベルでの話で、いわば座興や趣味のたぐいである。ノーギャラとはいえ、プロと同じ舞台に立つのはどう考えても無理があり、気がすすまなかった。
そんな僕の倒錯した思いとは無関係に、ライブの当日は否応なしにやってきた。場所は六本木の大手ライブハウス。その頃僕は係長職としてたくさんの仕事を抱えていて、日曜以外にあまりギターで歌う時間はなかった。それでも何かやらねばならない。
ライブが始まった。たぶん何もしゃべらずに、いきなり歌い始めたはずだ。ところが、声がまるで出ない。得意の高音が伸びないのだ。客席の最前列には同じ会社の社員が「動員」されていたので、歌い出すと同時に盛大な拍手が起きたが、それはいわば儀式のようなものに過ぎない。舞台の上で僕は自分の不調を瞬時に察知し、凍りついた。
真打ちとして最後に登場したプロの歌手の歌は、さすがに見事なものだった。僕が最も違いを感じたのは、声量の差である。その夜の僕がその面で特に劣っていたので、なおさらだった。 これが記憶に残る僕の最大の失敗ライブの一部始終である。
1981年12月、僕は32才で会社を辞め、故郷北海道に戻って建築デザインの会社を設立することになった。いわゆる「脱サラ」というヤツで、そのてん末はこのサイトの別のコーナーにも詳しい。 引越しは翌年の2月末で、直前になって妻の兄弟姉妹が全員集まって、盛大な送別会を開いてくれた。身内の間でも僕の歌とギターは知れ渡っている。主賓でもあり、何か歌わせられるのは目に見えていた。 送別会の場所は妻の実家で、自宅から歩いて15分ほどの距離だった。 「ギターを持っていこうかな…」妻にそう相談すると、「重くで邪魔よ。頼まれたら、無伴奏で歌えば?」とつれない。東京生まれで東京育ちの妻にとって、身内との別れはやはり辛いのだ。そう思いやると、素直に妻の言葉に従うことにした。
宴が進んで、当然のように「菊地さん、お別れに何か歌ってよ」と、声がかかった。歌はかぐや姫の「なごり雪」に決めていた。「別れ」そして「雪」、冬の送別の場に、これ以上ふさわしい曲はない。この曲はイルカも歌って大ヒットし、誰もが知っている歌だった。 「披露宴のときはたいしたことないと思っていたけど、今日の歌は気持ちが入っていて、さすがにうまいと思ったよ」
いつも歯に衣きせぬ口調の義兄の一人が、そう言って珍しくほめてくれた。しみじみとした心に残る送別会だった。 (次回で一段落します) |
 危険な二人 /1975
危険な二人 /1975
 向い風 /1976
向い風 /1976
