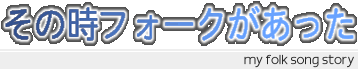 その4 .......
1974年、フォークデュオ「TOM&HIRO」の活動は2年目に入った。部費などの援助は皆無だったが、練習場所は会社の施設である社員寮だったこともあり、僕たちはあくまで社内バンドの位置づけだった。 噂を聞きつけた上司から、時折演奏の「業務命令」が出ることがあり、要請があるとどこでも歌った。はっきり覚えてないが、月に一度くらいのペースで歌っていたと思う。 歌う場は、社員旅行の宴会、下請け業者対象の安全協議会後の慰安会、全国支店長会議後の食事会、誰かの送別会など雑多で、何かといえば狩り出された。ときには何の予告もなく、いきなり「いまから社員食堂に来て何か歌ってくれ」ということもよくあった。
先にふれたように、こうした会社内の不特定多数が対象のライブでは、基本的に誰も知らないオリジナル曲はやらず、耳障りのいい一般受けする曲を選んで歌った。当時、二人でよく歌ったのは、井上陽水やかぐや姫の曲である。社内で反体制フォーク、反戦フォークのたぐいはご法度で、陽水やかぐや姫ならその禁にもまずふれない。
 伊豆の社員旅行の舞台にて/1974.6
この頃から僕は、アルペジオ奏法以外はピックを使って弾くようになった。ピックを使ったときの音の歯切れのよさが気に入っていた。この「夢の中へ」や、先に書いたオリジナルの「九月の風」のように、テンポの早い曲がレパートリーに増えたせいもある。アップとダウンを細かく混ぜる激しいストローク奏法でも、ピックなら耐えられた。
このピックはつい最近まで30年もずっと使っていたが、陽水の「東へ西へ」を歌っているとき、調子にのり過ぎたせいか、はたまた寿命だったのか、演奏中にまっぷたつに割れた。楽器屋に行っても同じものはどうしても見つからない。勧められた別製品を試しても、どうもしっくりこない。
HIROとのライブ活動は続いていたが、僕の部屋を起点とする彼とのオリジナル曲作りは、1973年の冬を境にぱたりと途絶えた。記録を調べても、1973年12月以降の二人の合作は、「人間らしく」という曲を最後にひとつもない。 理由はごく簡単で、二人とも親密な女友達が出来てしまったからである。土曜日曜はもちろん、時には平日さえもデートに明け暮れていた。このあたりは今も昔も変わることのない、若さの図式だろう。 必然的に、夜毎のミニライブは滞りがちになる。もっと格好よく言えば、わずか6ヶ月足らずで20曲以上のオリジナル曲を生み出し、二人とも燃え尽きてしまった部分もあったのかもしれない。
話がまたまた横道にそれるが、当時の僕の恋人はいまの妻である。しかし、なれ初めは音楽ではなくブンガク、つまり本だった。同じ会社の先輩OLだった彼女は、当然僕の歌を知っていたが、別にそこに惹かれたわけじゃないわ、といまでもはっきり言っている。
当時、ギターを弾きながら歌える男は、間違いなくもてた。「もてたい」という一心からギターを始め、フォークのたぐいを歌っていた連中もたくさん知っている。「そういうお前はどうなんだ?」と問われると、結果は別にして、動機としては明確に「違う」と断言出来る。おそらくHIROにもその邪心はなかったはずだ。
1974年7月、突然HIROに広島支店勤務の辞令が出た。東京と広島とではあまりにも遠すぎる。辞令は「TOM&HIRO」のユニット解散と活動の中止を意味していた。 僕の発案で、急きょそれまで作ったオリジナル曲を集め、自主製作アルバムを作ろう、ということになった。時間と金の制約でスタジオは借りられず、場所はいつもの僕の部屋である。暑い夏の盛りに、1ヶ月を要して連日のレコーディング作業が繰り広げられた。 このときのテープがいまも大切にとってある。部屋の条件は最悪だったが、古いシーツを壁に吊るし、少しでも音を良くしようと工夫した。音響機材はそれなりにそろえてあったので、音質はまずまず。ちゃんとしたステレオ録音である。 アルバムタイトルは以前ふれたように「九月の風」で、曲順のトップも飾った。テープのもう片方の面は、それまであちこちで二人で歌っていたカバー曲だけを集めた。
まず長いテープを回しっぱなしにし、二人で自由に歌った。同じ曲を何度も歌い、そのうちの最も出来がよいものを採用、というやり方だった。そのときの気分で歌詞やメロディを変えたり、アドリブで語りや即興詩を随所に入れたりした。
オリジナル曲は厳選した11曲で、うち7曲がHIROとの合作だった。それぞれが単独で作った曲も4曲含まれている。
残念ながらこの曲の作詞は僕でもHIROでもなく、詩の季刊誌に掲載されていた若い女性の作品である。「たくさんの人と会い、たくさんの人と別れたが、それでも私はまだ何かを待っている」といった内容の詩で、二人ともエラく気に入ってしまい、あれこれ議論しながら曲をつけた。
この「待っているうた」は、その後ソロでも随分歌った。そのときHIROが冒頭でやったスキャットを、いつもラストに入れて歌う。つい最近の我が家でのミニライブでもそれを披露した。
8月にHIROが広島に去ったあと、僕は一人黙々と曲作りに励んだ。秋に婚約したこともあり、僕にしては珍しく愛の成就をテーマにした曲も作った。 記録を調べると、この年の冬までに10曲近くを一人で作っている。それまでHIROとコンビで歌うバランスを考慮し、やろうと思って出来なかった実験的な曲作りを、ここで一気に形にした。
「月夜の晩に」という詩には、メロディが同時にふたつ出てきた。片方がしっとりとしたアルペジオ奏法の曲、もう片方が軽いストローク奏法の曲で、どちらにも絞り切れず、結局同じ歌詞とタイトルで、メロディの違う作品がふたつ生まれた。
本を読んで刺激を受け、そのイメージをそのまま曲にしたのもこの時だった。大江健三郎の「見る前に跳べ」という小説を読んで作った、タイトルそのままの曲である。僕には珍しく、激しいロック調の曲で、当時のテープを聴き返すと、まるでピックが割れそうな勢いで歌っている。
(ちなみに、岡林信康の同名タイトルのLPとは無関係である)
このとき作った曲を一人でレコーディングし、広島のHIROに送った。しばらくしてHIROからも数曲のオリジナルが入った短いテープが届いたが、僕と二人でやっていた時と比べると、いまひとつ物足りない感じだった。もしかするとHIROも僕のテープを聴いて、同じ印象を持ったかもしれない。
1974年11月、神奈川と山梨の県境にある大きな現場の辞令が、今度は僕に出た。東京から電車で2時間以上もかかる山深い場所で、社員寮から通いながらの現場管理は到底不可能である。自宅が神奈川にあった現場主任の上司は車での通いだったが、身軽な独身の僕だけは、現場の目の前にある民家に下宿させてもらうことになり、鞄ひとつですぐに赴任した。いわゆる、「現場常駐」である。 神奈川県直轄の責任ある仕事だったので、仕事ひとすじの意気込みでギターは持っていかなかった。しかし、何かの巡り合わせか、この家にいた4人の子供たちが皆フォーク好きで、陽水や拓郎などのレコードはもちろん、立派なフォークギターまで持っている。 いつもの僕なら、しめたとばかりにそのギターに手を出しただろう。しかし、現場の工程が大変厳しく、普通なら無理なコンクリート打ちの工程を、どうしてもその年のうちに終らせなくてはならない。昼の現場管理の仕事が終って夕食をすませると、ただちに現場事務所に戻って深夜まで施工図作成という毎日で、とてもそんな余裕などない。
暮れも押し詰まった12月28日、普通ならコンクリート工場は年末休暇に入っているが、会社からの特別な計らいで、その現場のためだけに操業。まだ薄暗い朝5時から作業を開始し、夕方4時までかかって、合計300立米近いコンクリートを、事故なく見事に打ち終えた。
宴たけなわとなった頃、一家の末っ子の男の子が部屋の奥からギターを持ち出してきた。すかさずおばさんが、「菊地さん、何かひとつ歌ってよ」と僕にうながす。フォークの趣味のことを話した記憶はなかったが、誰かが教えたのかもしれない。もちろん断る理由など何もなく、気分よく二つ返事でギターを受取った。
このときの素晴らしく高揚した気分は、いまでもはっきりと思い出せる。下宿は古い造りの民家で、茶の間の中央に12人ほどが同時に座れる大きな掘りごたつがあり、中は電気ヒーターではなく、本物の炭が赤く燃えていた。その一角に僕は座り、長い時間をかけてフルコーラスを歌った。 以後、この曲を人前で歌ったことはない。さまざまな条件の整ったその日のような感動を越えることは難しい予感がするからで、その意味では生涯にただ一度だけの価値あるライブだったと言える。
僕のことを余程気に入ってくれたのか、その後おばさんから縁談話が僕に持ち込まれた。実はその相手とは、二人いたおばさんの娘のうちの一人である。僕よりも3つ下で、スタイルのいい美人。新宿にある建築の専門学校に通っていた。料理も得意で、週に何回かは僕に食事の用意をしてくれていた。技術者で固い性格の僕は、娘の相手としては絶好に映ったのかもしれない。 すでに婚約していた僕は、もちろん丁重にお断りしたが、「もっと早く菊地さんに巡り会っていれば…」と、しきりに残念がられた。 この一家とは、結婚後もしばらく交際が続いた。時折くるおばさんからの電話で、「さだまさしがテレビに出ると菊地さんの事を思い出して、つい涙ぐんでしまうんだよ〜」といつも言ってくれていた。 現場が無事完成し、下宿を出る頃になって、曲がひとつ出来た。現場周辺の豊かな自然と静かな暮し、そしてこの一家とのふれあいをイメージして作った曲だ。 作った当初は、「…の四季」と、ずばり下宿先の地名を入れたタイトルだったが、最近になって聴く側にイメージを固定させないよう、タイトルと歌詞の一部を変えた。歌詞の中に「人間」を登場させたのもごく最近で、これは息子のアドバイスである。
この曲はのちに社内のソロライブで何度か披露したことがあるが、「メロディが美しい」と、大変評判が良かった。
1975年4月に、僕はいまの妻と結婚した。結ばれるきっかけは音楽ではなかったが、結婚式はありきたりではない手作りの音楽スタイルで、しかも披露宴のプロデュースは自分でやろうと心に決めた。「ありきたりではない手作りのスタートを切りたい」という考えは、二人の間でもぴたり一致していた。 現場の休みを有効に使い、式場探しに始まる細かい打合せを二人で分担しながら続けた。式の案内文も自作、ケーキカットや花束贈呈もなしで、3万円も払って当時はまだ珍しかったキーボードの生演奏を入れた。選曲はシーンに合わせ、すべて僕が決めた。 いまではこうした式の構成は少しも珍しくない。しかし、当時は銀座のど真ん中の式場でさえ、僕のアイデアを話すと、「そんな話は聞いたことがありませんが…」と、係員は首をかしげて戸惑いの表情を見せた。
目玉はラストの僕と彼女による挨拶で、これまた当時は常識破りの演出だった。しかも、挨拶に続けて僕が作ったオリジナル曲を二人で歌うという趣向である。
結婚したんです 1975.3 作詞/作曲:菊地友則
朝の光が 窓辺を照らし
結婚したんです 結婚したんです 結婚したんです
僕のそばで 君が紅茶を沸かし
※結婚したんです 結婚したんです 結婚したんです
二人とも何かと忙しく、二人そろっての練習は2回くらいしかやっていない。しかし、本番は若さの勢いで乗り切った。
 結婚式披露宴にて/1975.4 単なる一サラリーマンの結婚にしてはかなり型破りの披露宴だったが、「僕たちはこれからこうやって生きてゆきます」という周囲への宣言には、間違いなくなっている。こういうスタートを切れて良かったと、いま振り返ってみて、しみじみ思う。
この詩を読み返すと、それまでの僕の生き方と、それからの結婚生活に対するイメージが見事に表れていて、非常に興味深い。
結婚式には広島からHIROも出席してくれ、ソロでお祝いの歌を歌ってくれた。曲は井上陽水の「紙飛行機」で、はっきり言って結婚式にはふさわしくない。何しろ、「地面に落ちたり」「短い命」だったりする、はかない紙飛行機が主人公なのだ。 何を歌うか知らされてなかった僕も、席で内心はらはらしながらその歌を聴いていた。僕たちは気にしなくても、周囲の大人たちがとやかく言う可能性があった。
しかし、結果的にそのような声は皆無だった。あまりにもHIROの歌の出来が良かったからで、激しいストロークでシャウトするHIROの歌には、有無を言わせぬ説得力があった。
結果的にこのときが、HIROとの最後のジョイントライブとなった。理由はいろいろあって、一言ではとても語りきれない。
どんなに激しく燃えた炎も、やがては衰えて消え、そして白い灰に変わり果てる。万物は絶えず流れていて、決してひとつの場所に留まってはいないのだ。もちろん、人も社会も、そして宇宙でさえも、その例外ではない。 (もう少し続きます) |
 夢の中へ /1974
夢の中へ /1974
 人間らしく /1974
人間らしく /1974
