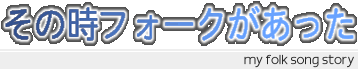 ����3 .......
�@1973�N4���A�l�͖k�C������㋞���A���������v�����g�̍H���Z�p�҂Ƃ��ē������ƂɂȂ����B�t�H�[�N�Ƃ͉����䂩����Ȃ������̂͂����������A�������Ј����̐H���̕Ћ��ɁA������̂Ȃ��t�H�[�N�M�^�[���A�܂�Ŗl��U���悤�ɂۂ�ƒu���Ă���B �@�l���w������ɒe���܂����Ă����M�^�[��2�䂠���āA�ǂ�����蕨�������B�ŏ��̓N���V�b�N�M�^�[�A���̓t�H�[�N�M�^�[���������A2��ڂ̃t�H�[�N�M�^�[�̓l�b�N���傫���Ȃ��Ă��āA���������܂Ƃ��ɒ���ƃn�C�R�[�h���S���������Ȃ��B��ނȂ��A4�`6�������͒��͂̎ア�K�b�g�����Ă��̂��Ƃ�����Ȃ���Ԃ������B �i�������A�M�^�[�����e���ł��l����������͉̂̂���A�Ǝv�����苭�����Ă݂悤�j �@���R�A�ו��̒��ɃM�^�[�͂Ȃ��B�Ј����ɂ���M�^�[����ɂƂ��Č���ƁA�l���g���Ă������̂��A�͂邩�ɗ��h�Œe���₷���B�V���Ј��Ȃ̂Ŏ��Ԃ͂����Ղ肠��A�ɂɂ܂����ă|���|������Ă���ƁA�߂��Ƃ�����̂�����Ɍ������Ă��܂��B
�@1�T�Ԃ����āA�Ј����ł̐V���Ј����}��J���ꂽ�B���ȏЉ�̂��ƁA�����Ȃ�V���Ј��ʼn����]�������A�Ɨ������疽�߂��ꂽ�B�Ј����ɓ������V�l��3�l���������A�l�ȊO�̓�l�͍����ł܂��ꊵ�ꂵ�Ă��Ȃ��̂��A���W���W���Ă��ނ����܂܂��B
�u�t�H�[�N�����������}�c�_������A�����Ə���v�Ɨ��ꂳ�����グ�A�������A�����ƊJ�X�x�Ə�Ԃ̃t�H�[�N�����A���Ȃ������Ē����Ȃ�����A�ȂǂƘb�����ȕ����ɔ��W����B
�u�J����~��v�͂ƂĂ��D���ȋȂŁA�u���傤���Ȃ��c�v�ƃ��t���C������t���[�Y�����Ƃ��������悢�B�u10�N�Ɉ�x�o�邩�łȂ����̖��ȁv�ƌ������Ă���l��������B �@�Z���K�̋Ȃ́u�ʉe������v���悭�̂��Ă��āA2�ȂƂ��Õ����Ă����B�������̂���{�[�J���̋y��P���̐����ƂĂ��D���������B�L�[����Ȃǂ������ɍ����Ă������A������L����ЂƂ̐��E���̂̒��ō\�z����Ă��āA�����ɑ傫�Ȗ��͂��������B
�@�V���Ј��̊��}��̂��ƁA�����y���畔���ɗU��ꂽ�B�����������Ȃ�����Ƃ����B�Â������̒��ŐԂ�����X�e���I����A������Ƃ������C���g���������B���z���́u�P���Ȃ��v�������B �@���O�����͒m���Ă������A�Ȃ��͎̂n�߂Ă������B�Ռ������𑖂����B�Љ�̌��ۂɎ����X�����A�u�����ǖl�̖��́A�����̉J�Ȃv�Ƃ����t���[�Y�ɁA�C�������h�ꓮ�����B �@�����ɂ͂��̐�y�̂ق��A�l�ƈꏏ�ɓ������V�l��l���Ă�Ă����B���͓�l�Ƃ��M�^�[���e���āA�t�H�[�N���D�����Ƃ������Ƃ����̂Ƃ����������B��y�������Ă̓t�H�[�N���ɏ������Ă����Ƃ����B
�u������x�t�H�[�N�����Ȃ����v
�@2�T�Ԍ�̋������A�a�J�̊y��X�ɑ����ăM�^�[�����B���߂Ă̋����̒�����A�w������ɐe�����Ă�������Ԃ��ƁA�茳�ɂ�2���~�����c��Ȃ��B�S�����͂����āA���[���X�̃t�H�[�N�M�^�[�����B�l�����߂Ď�ɂ��鎩�������̐V�i�̃M�^�[�ŁA30�N���������܂ł���ɒe���Ă���B �@�قǂȂ����ē�����HIRO���t�H�[�N�M�^�[�����B�d�����I�������Ƃ̖��x���ɂ́A����HIRO���n�߂Ƃ��闾���̃t�H�[�N�D���̘A�����l�̕����ɂ��ނ낵�A�l�̕��������R�Ƀt�H�[�N���̊����̏�ƂȂ�A���������C�u���[���ƂȂ����B
�@�����l�͊���ʓ����̏����ƁA�w������ɕ����Ă������z�ƎЉ�l�Ƃ��Ă̌����Ƃ̃M���b�v���炭��W�����}�Ɋׂ�A���Јꌎ��ɂ́A������u�܌��a�v�ɂ���Ă����B�܂��e�����F�l�����Ȃ��ǓƂȓs��̋��ԂŁA���ꗎ�������ɂȂ�l���~���Ă��ꂽ�̂��A�ԈႢ�Ȃ��t�H�[�N���B �@���R�����k�C���o�g������������HIRO���A�����炭�����S���������̂��Ǝv���B�ł����������l�̕����ɒʂ��Ă����̂��ނŁA�₪�Ăǂ��炩��Ƃ��Ȃ��A��l�Ń��j�b�g��g�����A�Ƃ����b�ɂȂ����B���̌�2�N�߂��ɂ킽���Ē����Г��Ŋ������邱�ƂɂȂ�t�H�[�N�f���I�A�uTOM��HIRO�v�̒a���ł���B
�@�l����5�ΔN�����������AHIRO�̉��y�Z���X�͔��ɂ悩�����B�̂��M�^�[�����܂��A����܂ŏo��������ԂƂ͂ЂƖ��Ⴄ�������������B
�@�ŏ��̓t�H�[�N�m�[�g�ɃX�g�b�N�̂���R�s�[�Ȃ������ς�̂��Ă����B���\�̏�͉�Ђ̉���Ȃǂ��ЂƂ܂��z�肵�Ă����̂ŁA�܂�ŒN���m��Ȃ��}�j�A�b�N�ȋȂ͊O���A�����̂����Ȃ��t�H�[�N�ɂ�����炸�A�s�b�N�A�b�v�����B
�@�܂��AHIRO���t�x�݂ɍ��������Ƃ����I���W�i�����̂����B�����ϔO�ɑ���߂��Ă���C���������A�Ȃ͈����Ȃ��B����Ȃ�l�����ӂ̎��������AHIRO�ɋȂ����Ă��炨���A�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�J���~���Ă� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1973.5�@�@�쎌�F�e�n�F���^��ȁFHIRO
�@�J���~�����@�J�T����������
�@�G�ꂽ�R�[�g���ʂ����Ă�ꂸ�@���䂭�l�͍K���̃p���\��
�@�J���~�����@�J�T����������
�@�ǂ����Ă��Ƃ��Ȃ����������̋Ȃ����A�e�[�}�Ɂu�J�v�������Ă���������A���炩�Ɂu�J����~��v��u�P���Ȃ��v�̉e�����݂���B�Ȓ��͂����܂ŃA�b�v�e���|�ŁA�l�̎����Ă����C���[�W�Ƃ͂��Ȃ����Ă����B�������A���ۂɉ̂��Ă݂�ƂȂ��ށB
�@6���Ɋw������̗F�l�̌��������D�y������A�����ꂽ�̂ŋA�Ȃ����˂ďo�Ȃ����B���Ȃ葁������F�l�̏o���v�����Ă��āA�w������ɐ�^�𗁂т����́u�̗w���v���Ăт�낤�Ǝv�����B���̓��̂��߂�5���̋����ŃM�^�[�̃n�[�h�P�[�X��1��5��~���o���Ĕ����A��s�@�ł̈ړ��ɔ������B �@�d�b�œ�l�̂Ȃꂻ�߂���ނ��A�K���ȋȂ��s�b�N�A�b�v����B�������A�����܂Ŕ�I���̗]���Ȃ̂ŁA���Ԃ�10���ȓ��Ƃ����������������B��������ƁA2�Ȃ܂ł����E���B
�@���̂Ƃ��̓V�i���I����Ȃ̑I���ɑ����������B���߂ł����������̏�Ȃ̂ŁA�l�̓��ӂƂ���ʗ��̉̂Ȃǂ����Ă̂ق��B������ܑ̗B���h������A����Ӗ��ŌƑ��Ȏ�͎g���Ȃ��B�������A�u�n�b�s�[�v�̘A���ł��܂�Ȃ��B���Ƃ���l�̌˘f����܂Â��̕������o���A������������Ă䂭�ߒ����V�i���I�Ɏd���Ă������B
�s�̗w���EK�N��M����̂Ȃꏉ�߁t �@���̂Ƃ��̋q��70�l���炢�ŁA�݂ȐÂ��ɒ����Ă��ꂽ�B2�ȂƂ����̐��A�����ԉ̂ŁA�������q�Ȃ̗܂ȂǂȂ��B���ȃx���g���g���A�����ĉ̂������A�V�����M�^�[�̉��F�ɐ���������ꂽ�悤�ȋC������B
�@�F�l�͂ƂĂ����ł���A���l����⑼�̏o�Ȏ҂�����A�u�������ǂ�������v�Ǝ����グ��ꂽ���A�l���g�͕s�����c�����B�S�̂̍\���ɂ��܂ЂƂ[���o���Ȃ��������炾�B������̐S��h���Ԃ�Ƃ����_�ł��A������Ȃ����������B�������ޓ����e�[�}�ɂ����I���W�i���Ȃŏ�������悩�������ȂƁA���ܐU��Ԃ��Ďv���B
�@�����Ј����͑�c��̐����r�̋߂��ɂ���A�d�Ԃ�30���قǂ̏a�J�̊��y�X��HIRO�Ɠ�l�ł悭�s�����B�D�y�ɂ͂Ȃ�����ȃ��R�[�h�V���b�v��y��X������A����������Η~�������͉̂��ł���ɓ���X�������B �u�a�J�W�����W�����v�Ƃ����t�H�[�N�n�̉̎肪�o�v���郉�C�u�n�E�X�ɂ����x���s�����L��������B������Ŗ�������̕��c�S��̘H��R���T�[�g���A�ʂ肷����Ɂu�J���[���C�X�v�ŗL���ȃt�H�[�N�̎�A�������i�ɋ��R�o��������Ƃ�����B�i�T�C���͖��Ȃ������j�Ƃ������A�t�H�[�N�����̖l��HIRO�ɂ̓s�b�^���́A�h���ɖ������X�������B �@����Ƃ��A�a�J�̈�ԑ傫�ȃ��R�[�h�X�Ńt�H�[�N�̃A���o�������Ă���ƁA�N�₩�ȗΐF�ŗ��J���̕ς�����W���P�b�g���ڂɂ����B�v�킸���o���Ă݂����A�ʐ^�������Ȃ��C���X�g�����̊G�{�̂悤�ȃ��R�[�h���B�\���ɂ́A�u�y��P�����E�Y�ꂽ���b�v�Ƃ���B
�i�Z���K�̋y��P�����I�j
�u�J����~��v�u�ʉe������v�u�o���̉́v�ȍ~�̘Z���K�̍s���͂͂�����m��Ȃ������B�����A�������Ėڂ̑O�Ƀ��[�h�{�[�J���������y��P���̃A���o��������Ƃ������Ƃ́A�ނ����炩�̗��R�Ń\���������n�߂��ƍl���Ă悩�����B
�@����Ƃ��A�c�Ƃ̐�y�������Ȃ�h�A���m�b�N���A�ŋ߂��O���p�ɂɒ����Ă��郌�R�[�h�̂��ƂŘb������Ƃ����B���Ă͂��܂�ɓ����Ȃ��肤�邳�����x��������̂ŁA���������ɂ���Ƃ��������肩�Ǝv�������A�b���͑S�����ŁA���͂��̃��R�[�h���������������̂����A���炭�݂��Ă���Ȃ����H�Ƃ̗v�]�ł���B
�@��y�͖����̂悤�ɒ����Ă���l�q�������B���ɋC�ɓ����Ă����炵���̂��A�u�������Ă������Ȃ���v�ŁA�H���ł��@�̂��o��قǂł���B
�u�e�n�A���̃��R�[�h�̖��O�Ɖ̎��������x�����Ă���Ȃ����v
�@�G�߂�����A�l������Ɏd����s��ł̐����Ɋ���Ă����B�l�̕������N�_�Ƃ���HIRO�Ƃ̃Z�b�V�����͘A�������Ă��āA�^���̋@�ނ�}�C�N�A�����ă��R�[�h��ȂǁA���X�̋����̑唼�����y�ɏ����Ă��������A�A���̎c�Ƃŋ������͏[���ɂ���A���]�ԕ��Q���s��|���̎�����łɂ�߂Ă����̂ŁA�����x��͂Ȃ������B �@���̎����A���ɐ��Ȃ̗ʎY�y�[�X�ŃI���W�i���Ȃ����܂�Ă����B���̑唼�͖l�A�����ċȂ̑唼��HIRO�̒S���������B
�@�����l�͋G�߂ɃG������������Ă��āA���ɊW�̂���Ȃ����ɍ�낤��HIRO�ɂ��������A�������Ǝ��������Ă����B
�@�㌎�̕� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1973.8�@�@�쎌�F�e�n�F���^��ȁFHIRO
�@�������������Ă�����@�����r���̌��Ԃ���
�@�������������Ă�����@�X�̌͗t��ǂ�������
�@��������������悤�ɁA�C���g���ł܂�6��������Ⴍ���Ȃ�悤�ɉ��x���k�킹�A���̌�ɑ����������X�g���[�N�œ���A�b�v�e���|�̋Ȃ��B�Г��̂������ւȃ��C�u�ʼn��x����I�������Ƃ�����B�L�[�͓���E�Ŕ��ɍ������A���Ɍy�X�Ɖ̂��Ă����B
�@���̋Ȃ̃R�[�h�i�s���uECECE�v�Ǝn�܂��āA�uG#mC#mEDE�v�Ƃ���ϑ��I�Ȃ��́B�������A���ꂪ���Ƀs�^�b�Ƃ͂܂��Ă����B �@����Ȃӂ��ɁA���ۂɉ̂��Ȃ���݂��ɕ]���������A������f�B�̓R���R���Ƃ��̏�ŕς���Ă������B�����炱�̓���������Ȃɂ́A�ꉞ�X�I�ɍ쎍�ƍ�Ȃ̒S����������Ă͂��邪�A���ׂē�l�̍���ƌ��������Ă��悢�قǂ��B |
 �J����~��� �^1973
�J����~��� �^1973
 �P���Ȃ� �^1973
�P���Ȃ� �^1973
