 ひとつぶの涙 /1972
ひとつぶの涙 /1972
1972年の秋、この新聞社のモニター会議で知り合った女友達から、職場のフォークサークルに入らないか、と誘われた。当時彼女は市の臨時職員をやっていて、市役所の会議室を借り、週一回のペースで仲間内でフォークライブをやっているという。
「僕なんかが参加してもいいのかな」と遠慮がちに尋ねると、
「あなたなら大丈夫よ、私が推薦するから」という彼女の言葉に甘え、電話がくると余程の用事がない限り、ギターを抱えて浮き浮きと出かけた。
メンバーは10人ほどで、男女がほぼ同数、僕以外はすべて社会人だった。このサークルのレベルは割に高く、全員がグループかソロで歌える力があり、歌も反戦フォークあり情緒フォークや爆笑フォーク(この二つは僕の造語)ありで、バラエティに富んでいた。
特に僕に声をかけてくれた彼女(仮に名前をミサキさんとする)がリードボーカルを務める女性3人グループの歌は秀逸で、シモンズやベッティ&クリスの歌を、ほぼ完璧にコピーしていた。ミサキさんが美しい声で歌う「ひとつぶの涙」には、その場にいる誰もを引きつける独特の魅力があった。
僕はここで黙って皆の歌を聞いているだけだった。部外者なので、自らしゃしゃり出る図々しさは、さすがに持ち合わせていない。すると頃合いを見てミサキさんが、「菊地さん、何か歌って」と声をかけてくれる。そこでようやく僕はしずしずと前に出て歌うことが出来た。
ある日の日曜、朝寝を決め込んでいると、いきなりミサキさんから電話がきた。
「私、いますごくいいことを思いついたの。菊地さんて、詩が書けたわよね」
うん、まあ少しは、と僕は半分眠ったままで答えた。いったいそれがどうしたっていうんだ、こんな朝早くから…。僕はもっと眠っていたかった。しかし、ミサキさんの声はエラく弾んでいる。
「菊地さんが歌える曲をいくつか選んで、その歌をつなぐような形で詩を作るのよ。つまり、ある大きなテーマを決めて、ストーリーを作る。それに沿った曲をいくつか選ぶ。曲と曲の間を詩でつないで、語るわけ。分かるでしょ?」
ああ、分かるよ、と僕は少しぶっきらぼうな調子で答えた。しかし、そんな言葉とは裏腹、このミサキさんの素晴らしい提案にすっかり心を奪われていて、眠気もどこかにすっ飛んでしまっていた。
「で、話はそれだけ?」
打ち明けると、僕の期待はもうひとつ別にあった。もしかしたらこのあと、デートの誘いがあるかもしれない…。
ええ、それだけよ。今度はミサキさんの少し沈んだ声が返ってきた。思っていたより僕の反応が鈍いのが、不満そうである。
フォークサークルに誘われたときから、もしかするとミサキさんは僕に関心があるのではないか?そんな淡い期待が僕にはあった。ミサキさんは僕より二つ年上だったが、あの菩提樹を歌ったときの音楽の先生のような黒い目をしていて、最初に会ったときから、どこか強く惹かれるものを感じていた。
おそらく僕のそんな密かな想いは、見えない電波で確かにミサキさんに伝わっていたのだと思う。
 サルビアの花 /1972
サルビアの花 /1972
ミサキさんの電話をもらったあと、僕の頭の中をひとつのイメージがぐるぐると回りだし、どうにも止められなくなっていた。多感だった僕は、周期的に独りよがりの恋を繰り返していて、ちょうどそのころも別の女友達との、手ひどい失恋に陥ったばかりだった。
(この恋のてん末を、ストーリーに仕立てあげよう…)
そう決断すると、ミサキさんの提案通り、まず簡単なストーリーをイメージして曲を4曲選び、全体を詩のような散文のようなものでつないだ。なぜ4曲だったのか?それは男女の出会いから別れを、四季のうつろいに合わせて描いたからで、曲の演奏時間や曲間の語りの時間を合わせると、20分強の程よいミニステージに仕上がるはずだった。
僕はミサキさんが発案したこの「歌謡劇」に夢中になり、「春夏秋冬」とみずから名づけ、日夜練習に励んだ。次のサークル内ライブで、予告なしにいきなり発表するつもりだった。
ほどなくしてミサキさんからミニライブのお誘いがきた。僕はすでに完成していた歌謡劇のことはおくびにも出さず、普段通り何気なく集まりに参加した。
メンバーの歌が一通り披露されたあと、いつものようにミサキさんの声が僕にかかる。いつもの僕なら、その日歌う曲は完全に暗譜してステージに臨む。しかし、このときは長い重要な語りが曲間に含まれているため、すべてを覚えきるには、少し不安があった。僕が初めて楽譜らしきもの(実は中身はシナリオ)を持ってステージに向かうのを見て、ミサキさんは一瞬怪訝そうな表情を見せた。
座るなり、いきなり語りを始めた。確かこのときは、「詩とギターによる構成、春夏秋冬」と冒頭で宣言したはずである。
「僕が彼女に最初に出会ったのは、もう4年も前の春のことです…」
そんな切り出しから始まる、ちょっとクサい恋愛話を、臆面もなく大真面目に語った。語りにはギターの音をアルペジオで小さく入れ、そのコード進行は実は次に歌う曲のコード進行と同じになっているという仕掛けである。
入りの時点で、聴き手の気持ちがぐっと自分に集まってくるのがはっきりと感じられた。(これはうまくゆく…)始めてみるまでは半信半疑だった出来映えが、曲の進行につれて自信に変わり、やがて自己陶酔の境地に入り込んだ。
聴かせどころは物語りが大きく展開する夏から秋の場面で、ここに、もとまろの「サルビアの花」を持ってきた。このときは下手なりにギター奏法にも気を配っていて、曲に応じてさまざまな奏法を混ぜていた。この「サルビアの花」は原曲の穏やかなアルペジオ奏法を無視し、「戦争しましょう」のときのような、激しいストローク奏法で歌った。全体の流れのなかで、それが最も適切と判断したからだ。
すべてを語り、歌い終えると、不思議な現象が起きた。いつものような拍手が全くなく、室内は奇妙に静まり返っていて、皆黙ってうつむいたままなのである。
我に帰った僕は、一瞬不安に陥った。(まさか失敗だったんじゃ…)
すると突然、ひとりの女性が両手で顔をおおって激しく泣き出した。小さな会議室の中に、彼女の泣き声が響きわたる。だが、誰もそれをなだめようともしない。僕は事の成りゆきをよくつかめないまま、ただ呆然とその場に座り込んでいた。
そのとき、サークルのリーダーの男性がすっと立ち上がり、僕に近寄ってきた。黙ったまま僕に手を差し出し、強く握りしめてくる。彼の目も赤く潤んでいて、それがすべてを物語っていた。
つまらないから拍手がないのではなく、皆深く感動してなにも言葉が出ないのだった。人は本当に悲しいときには涙は出ず、本当に感動したときには、言葉さえ出ないものなのかもしれない。
僕にもう拍手は無用だった。終わったあとの静かな沈黙と涙、歌い手に対するこれ以上の賛美があるだろうか。僕は幸せな歌い手だった。
 春夏秋冬 /1972
春夏秋冬 /1972
1ヶ月後、就職も決まり、卒業もほぼ決まった僕にとっての最後の大学祭が催された。大学祭には、市民会館の大ホールを貸し切り、音楽祭が大々的に開催される。卒業を間近に控えた僕は、かってないほどの賛美を受けた歌謡劇、「春夏秋冬」をひっさげ、エントリーすることを決意した。
参加者に対するオーディションはなかったが、音楽祭は一般市民にも広く開放されるため、冷やかし気分で出ることは許されない雰囲気があった。
まず歌う曲目を書類に記入して提出。リハーサルもちゃんとあって、照明効果なども細かく指定出来る。よく分からないまま、季節に合わせて青、緑、赤、白のピンスポットを順に指定。椅子に合わせて譜面台の高さとマイクの位置も低く指定する。あとはステージでおよその声とギターの音の感じをつかんでリハーサルは終った。
音楽祭当日、楽屋では他のグループが発声練習に余念がない。しかし、僕は学寮の自室で直前まで入念な発声練習を積んでいたので、何もすることがない。暇つぶしに印刷されたプログラムを見てみると、全部で11組のバンドが参加。フォークやカントリー、ロックやクラシックなど、バラエティに富んでいる。調べると、ソロは僕を含めて二人だけ。もう一人はカントリーで、フォークソロは僕だけだった。
僕の出番は4番目で、全部で4時間あるプログラムの第1部ラストひとつ前という、願ってもない順番だった。
舞台横から客席をのぞいてみて、びっくりした。1000席は超えるだろうと思われるホールが、7割方埋まっているのだ。工業大学なので客層は当然ながら男子学生が主体だが、地元にあった短大生、各種学校生、高校生の姿も多数見られる。平日の午後5時開演だったため、社会人らしき姿はあまり見られなかった。
ミニライブのときと客層が違うことに一瞬不安を感じたが、ここでじたばたしてみても始まらない。まな板の上の鯉の気分で腹を決め、静かに出番を待った。
このときは最初の野外ライブのときと違って、ほとんど前宣伝はしなかった。極めて私小説に近い内容を披露しなくてはならないので、普段の仲間に聞かせるのは、さすがにばつが悪い。
1組20分の演奏時間だったが、すぐに順番が回ってきた。ところが、幕が上がっていざ始めてみると、どうも観客の様子がおかしい。語りの中のちょっとした言葉に、微妙に会場がざわつくのだ。最初から最後まで静まり返っていたミニライブのときとは、明らかに様子が違っていた。
これはあとになって分かったことだが、会場の大多数は僕を知らないか、ちょっと顔を見たことのある程度。ミサキさんのいる市のフォークサークルでのライブなら、皆僕の歌をちゃんと「聴こう」としてくれていた。だが、ここでは観客全員がそう好意的な聴き手ばかりではないことは明らかである。
語りの前半にある具体的過ぎる地名や急すぎる場面転換が、会場の遠慮ない失笑やざわめきを誘った背景は、どうやらそのあたりにあったらしい。
ステージの上で僕も本能的にそれを察知した。しかし、ここは何とか乗り切らなくてはならない。後半の「サルビアの花」から、ラストの「雨に消えた人」まで進めば、間違いなく自分のペースに持ち込める。そのためには、会場の反応に臆さず照れず、堂々と語り、歌い切るしかない。
そう思った僕は、会場のざわめきはしばし忘れ、淡々と自分のペースを守った。
 雨に消えた人
雨に消えた人
ここでこのプログラムの構成をもう少し詳しく説明したい。
1曲目「雪」〜猫
2曲目「Come to my bed side」〜岡林信康
3曲目「サルビアの花」〜もとまろ
4曲目「雨に消えた人」〜チェリッシュ
曲間はミニライブと同様に、語りを入れながら次の曲と同じコード進行のアルペジオでつなぐ。ストローク奏法とアルペジオ奏法を交互に入れ、味つけもそれぞれ変えて単調にならないよう、工夫をこらした。
物語りの部分は、自分の弾ける曲、歌える曲にあわせてかなりアレンジした。1曲目は単に好きな曲だったから、強引に雪の日に彼女と最初に出会うシナリオである。2曲目の難しい奏法は、ギターの苦手な僕にとっては大きな冒険だったが、この日に合わせて死ぬほど練習したせいで、何とか格好になった。(ただし、いまはもう弾けない)
出会いから触れあいに至る1〜2曲目までのシナリオは、完全な僕の創作である。いま読み返すと推敲不足で、アラが目立つ。会場から小さな拒否反応が出た理由は、おそらくそれだ。だが、3〜4曲目に至るシナリオは、まるで劇画のような衝撃的事実に基づくもので、リアリティがある。聴き手を文句なく揺さぶる説得力があるのだ。僕が後半に勝負を託した訳はそこにあった。
僕がかたくなに自分のペースを保って語り、歌い続けるうち、会場の反応が徐々に変わってきた。ちょうど、「Come to my bed side」の歌のラストの高音部を、ぴしりと決めたあたりからだ。会場が次第に静まりかえり、僕の語りを耳を澄ませて聴き取ろう、そんな空気がはっきりと伝わってきた。
(きたぞ…)と、僕は思った。ステージで歌っているとき、展開がうまく運び出すと、僕と客席の間に無数の見えない蜘蛛の糸のようなものが投げかけられ、僕はその糸をあやつって聴き手を自在に導くような錯覚にしばしば陥る。このときもまさにそれで、1000人近いであろう聴衆の前で、僕は巧みな人形使いに成りきっていた。
4曲目の「雨に消えた人」は、自分で工夫したアルペジオを語りの部分から入れ、そのまま曲へするりと入っていった。
実はこの「雨に消えた人」は、自分では一度も聴いたことがなく、あの加川良のアルバムを持っていた友人から教えてもらった曲だ。しかし、聴いた瞬間、いい曲だな、と直感した。ミサキさんからこのプログラムのアイデアをもらったとき、迷わず最終曲に使おうと思った。かなりアレンジして歌ったはずだが、ラストの4行が実に泣かせる。気持ちを込め、抑揚をつけてていねいに歌った。
このとき、客席の前部はほんのりと明るく、ステージから幾人かの女性が涙を流しているのが、はっきりと見えた。僕はなぜかミニライブのときのように陶酔しきってはいず、熱唱しながらもどこかさめた部分で、そんな聴き手の反応を冷静に見つめていた。
プログラムが終ると、長い拍手が続いた。よく立て直したな、と自分で思った。半分崩れ落ちそうになりながらも、何とか持ちこたえて終らせた。ミニライブでの評判に甘え、聴き手に合わせたシナリオの再検討を怠った僕の、ちょっとほろ苦く、しかし充実した学生時代最後を飾るライブの思い出である。

大学祭音楽フェスティバル「春夏秋冬」/1972.11
「シナリオでいくつかの曲をつないで順に語る」というこの歌謡劇の手法は、つい先日、小椋佳が全く同じスタイルでコンサートでやっているのを、NHKのテレビで観た。もともとはあのミサキさんが僕に仕掛けたことが発端だ。だから、この歌謡劇とミサキさんとを切り離して語ることは出来ない。
ミサキさんとはなぜかそれきりになってしまったが、彼女のことをすべて語ると、おそらく一編の恋愛小説になる。たぶんミサキさんは僕のことを、よく理解してくれていたのだと思う。

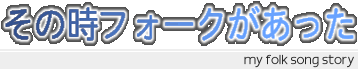
 旅の宿 /1971
旅の宿 /1971
 さなえちゃん /1972
さなえちゃん /1972

