初の野外ライブで熱唱
 菩提樹 /1962
菩提樹 /1962
「ぜひ音楽の道をめざしてください」
僕の小さな自尊心をくすぐるそんな甘い言葉をみつけたのは、中2のときにクラスで回覧された、僕あてのサイン帳の中である。生徒数の増大で学校がふたつに分かれることになったとき、中1のときからずっと同じクラスだった二人の女生徒が記したものだった。
なぜそんな言葉を書き残したのか、彼女たちとはそのまま別々の学校に分かれてしまったので、実ははっきりしない。ひとつだけ思い当たるのは、学校の音楽の時間での、ある出来事だ。
小学校の頃から音楽の成績は良く、通信簿もたぶんずっと5だったと思う。しかし、成績が良いことと、好きであることは別物だ。僕が好きだったのはもっぱら算数と図工で、音楽の授業にそれほどの関心があったわけではない。
中学校に入ると、周囲の男子生徒は徐々に声変わりをしてゆく。身体が小さく、二次成長も遅かった僕は、声変わりには無縁で、いつまでたってもかん高い少年の声のままである。それが次第に自分の中で大きなコンプレックスになっていた。音楽の時間も苦痛の時間に変わりつつあったが、集団で歌うときは女子の声に紛れて、かん高い声もそう目立たない。
中1の秋ころに音楽の教育実習生がきて、たまたま僕たちのクラスを担当することになった。ある日の音楽の時間、曲はシューベルトの菩提樹だった。僕の好きなスローバラード風の曲調だ。ラストの高音部が心地良い。いい気になって大声で歌っていたところ、その実習の先生(女性)がピアノを弾く手をふと休めた。
「誰かいい声を出しているなあ、誰かな…」
そう言ってクラスをぐるりと見渡す。その視線が僕にぴたりと止まった。
「君かな?君でしょう。ちょっと立って一人で歌ってごらん」
そう言って先生は黒い目でじっと僕を見た。打ち明けると、僕はその先生に秘かに憧れていた。僕はその目に吸い寄せられるように立ち上がった。先生のピアノが始まる。
「泉に沿いて 茂る菩提樹 慕い行きては うまし夢見つ…」(近藤朔風訳詞)
臆せず、ソロで歌い切った。元来僕にはクソ度胸のようなものが備わっているようで、ここ一番に妙に強いところがある。先生への憧れもきっと後押ししてくれたに違いない。
「君はとてもいい声してるよ。もっと歌の勉強するといいわ」
歌い終ると、確かそんな事を先生は言ってくれたと思う。人前で初めてソロで歌い、拍手までもらった、ちょっと晴れがましく、くすぐったい少年時代の記憶である。
先生の言った「勉強」とは、もしかしたら本格的な声楽の勉強のことだったのだろうか。サイン帳にメッセージを残してくれた二人の女生徒は、おそらくこのときの先生の言葉を、忘れずにいてくれたのだろう。
 白いブランコ /1969
白いブランコ /1969
「音楽の道をめざして…」などと思いがけず同級生から持ち上げられたりしたが、もちろん音楽で生計を立てるつもりなどなかった。
中3のとき、別の音楽の先生から、「合唱部で男子生徒が足りないから、発表会のときだけ手伝って」と頼まれ、渋々引き受けたこともある。声が大きく、音程も割にしっかりしていたので、音楽の先生からはそれなりに評価されていたようだ。
しかし、中学校が終り、高校に入学するころになっても、相変わらず声はボーイソプラノのままだった。僕は相変わらず声のコンプレックスに縛られていて、高校の芸術科目でも音楽ではなく、迷わず美術を選択した。
担当の美術の先生は、北海道の美術界では名の知れた方で、好奇心にかられて勉強した僕は、それなりの成績を残した。その美術の時間に教えられたいろいろなことが、いま建築設計という本職でどこか活きているような気がするから、このときの選択は決して間違いではなかった。
僕が完全に声変わりを終えたのは、なんと高2になってからのことである。もしこれがあと3年くらい早ければ、ひょっとすると僕の運命は、もう少し別の方向に動いていたかもしれない。
僕は一浪のすえ、第2志望の地方の工業大学に入った。専攻は機械で、音楽とも美術とも無縁である。サークルは4年間弓道部で、これまた芸術とは程遠い。そんな僕の運命を大きく左右する出来事が、20歳の冬に起きた。
すぐ上の姉が結婚することになり、札幌で式をするので、出席するように連絡がきた。前日に実家に戻ったが、当の姉がいきなり、「明日何か歌ってよ」と僕に頼んできた。披露宴で新婦側の余興をやる人間が少なく、バランスが悪いので弟の僕が急きょリストアップされたらしい。
「もう司会者には言ってあるから」と、有無をいわさぬ口調。はっきり言って困った。人前で歌った記憶は、中1のときの「菩提樹」以来、7年間皆無である。いきなり歌えと言われても、いったい何を歌えばいいのか…。
だが、迷う時間はあまりなかった。結婚披露宴という場に大きく外れてなく、しかも20歳という自分の年齢にふさわしい歌というと、そう候補は多くない。家の誰にも知らせなかったが、(白いブランコでいこう…)と、このとき即断した。
「白いブランコ」と書くと、覚えている方も多いだろう。日本のフォークの黎明期に一声を風靡した、ビリーバンバンの名曲である。この曲もスローバラード調で、なぜか歌詞とメロディは完璧に覚えていた。あれこれいいつつも、やはり歌はずっと好きだったのだろう。
式の当日、披露宴の出席者は150名近く。そして7年間のブランク。ビビる条件は整っていた。まだカラオケのない時代で、アカペラ(無伴奏)である。しかし、ここでも僕は堂々と歌い切った。そして「菩提樹」を歌ったとき以上の喝采を浴びた。
式のあと、いろいろな人から反響があった。
(オレって、けっこうやれるんじゃないか?)
そんな大それた思いと自負心とが、じわり沸き上がっていた。
 小さな日記 /1970
小さな日記 /1970
大学に入って2年目、当時ブームだった深夜放送で、フォーク専門の若いDJがいて、毎週聴くようになった。何気なく選んだ「白いブランコ」もそうだが、このときすでにフォークというものに、大きく惹かれるものを感じていた。
この番組で、「誰でも歌えるフォークソング」というコーナーがあり、全くの素人でも歌える曲を毎週ピックアップし、ギター伴奏つきでていねいに解説してくれる。
当時入っていた学生寮の部屋にあった半分壊れたギターで、みよう見まねでギターを弾いてみた。そんな気に突然なったのも、姉の結婚式での思いがけない喝采が伏線になっていたのは間違いない。
いわゆる「コード」というものを覚えたのも、このころだ。最初に覚えた曲がいまでも楽譜に残っている。キャッスル&ゲイツの「おはなし」という曲で、基本コード5つで簡単に弾ける、というふれこみだったが、当時の僕はFのコードがうまく押えられず、FやGがやたら出てくるこの曲を歌った記憶はあまりない。
当時覚えた曲でもっともよく歌ったのが、フォー・セインツの「小さな日記」である。AmDmE7のごく簡単なコード進行が基本で、Fはわずか1個所、とても弾きやすかったのがその理由だった。
そのころはまだピックをもっておらず、もっぱら指だけでポロポロやる、いわゆるアルペジオ一辺倒だった。ごく簡単なものだったが、ラジオの声の解説だけで何とか物になったのだから、好奇心や執念は馬鹿に出来ない。
こうして徐々にギターをつまびけるようになった。「新譜ジャーナル」や「Guts」というフォーク系の音楽雑誌を友人の下宿や喫茶店で見つけると、新しいコードや歌詞を素早くメモし、レパートリーに加えた。表紙にベートーベンの描かれた自分の「フォークノート」には、こうして次第に曲が増えていった。
そうこうするうち、ラジオなどから流れてくる歌をメモし、自分でコードをつけて歌う、という技をしらずしらず会得した。これは自分でもよく分からないが、勘で何となくコードがついてしまうのである。勉強の成果ではなく、単なる音感なのだろうが、ギターで何か歌ったことのある方は、ほとんどがこうした経験をお持ちだと思う。
当時の「フォークノート」を開いてみると、シューベルツやビリーバンバン、加藤登紀子や赤い鳥を好んで歌っている。
 また逢う日まで /1970
また逢う日まで /1970
1970年、岡林信康の「山谷ブルース」を聴き、軽いカルチャーショックを受けた。それまで歌っていた軽く、おだやかな世界とは異質なものを感じ、彼の歌ういろいろな曲をコピーして歌った。フォークにある社会に対するメッセージ性に強く惹かれるきっかけとなったのが、間違いなくこの曲だった。
いっぽうで、吉田拓郎に代表される、「自己の内なる世界へのメッセージ」にも同時に惹かれていて、この種の曲も数多く歌った。六文銭の「出発の歌」がレパートリーに加わったのも、このころだ。
1971年6月、住んでいた学生寮の寮祭で、「演芸ステージ」なるイベントが企画された。当時62室あった各部屋で何らかの出し物をし、審査員の採点によってなにがしかの景品が出るという。いわば「学習発表会・学生版」のような代物だったが、賞品欲しさに、大胆にも同室の男と二人で、歌を歌うことになった。
ただ歌うだけじゃ芸がない、菊地、お前がやっているギターで何かやれ、との話になり、まだ人前でギターを披露したことはなかったが、審査員(と言っても、全員学生)数人の前という気楽さもあって、舞台に立つ気になった。
曲目は相方の歌いやすさも考慮し、当時流行っていた「また逢う日まで」(尾崎紀代彦)と、「白い鳥に乗って」(はしだのりひことシューベルツ )である。ただし、僕が歌ったのは、2曲目だけで、それもサイドボーカルのみ。あとは伴奏に徹した。
フォークは好きだったが、「フォーク以外は一切歌わない」というこだわりはなく、気に入れば歌謡曲でも民謡でもなんでもこなした。当時のレパートリーを見ると、「コキリコ節」「叱られて」「雪の降る町を」など、さまざまなジャンルの曲がフォークの曲と仲良く並んでいる。このスタンスは、いまでも変わることはない。
さて、肝心のステージの出来だが、入念なリハーサルを重ねたにも関わらず、いざステージに立つと相方は僕の伴奏のペースを全く無視し、どんどん勝手に歌い進んでしまう。ギターそのものに大きなミスはなかったが、相方に合わせるだけでエラく苦労した記憶しか残念ながら残っていない。
苦労の甲斐あって、参加賞よりはかなり上の「酒一升」を景品でもらい、その夜は楽しい宴となったのだが、ともかくも人前でギターで初めて歌ったのが、このときの演芸会だった。

最初のステージ/1971.6
話が少し戻るが、この年の春、NHKで大人気だった「ステージ101」という歌って踊る音楽番組が、2期生を全国公募した。あちこちで持ち上げられていたこともあり、踊りはもともと得意だったこともあって、応募しようかと本気で悩んだ。
姉からも、「受けてみれば?」と勧められ、帰省した折に、母親に真面目に相談した。すると、「そういうことは、まずは大学を出てからでしょ」と軽くいなされ、力が抜けた。いま思い返すと、親に相談する時点で、僕は自信がない心中をすでに暴露していたことになる。母はそんな僕の先行きと才能を、見事に見抜いていたのだ。
 戦争しましょう /1971
戦争しましょう /1971
大学3年(1971年)のあるとき、高校時代の友人の部屋で加川良のアルバムを見つけた。それまでも「教訓 I」は耳コピーでよく歌っていたが、アルバムを聴いたことは一度もない。フォーク狂いの僕に感化されて買ったという友人は、当時札幌に住んでいて、レコードを借りることは難しい。そもそも、当時の僕はステレオをまだ持っていなかった。
話がそれるが、学生時代の僕は酒と弓道、そして自転車放浪旅行に明け暮れる日々で、少ない時間をやり繰りして稼ぎ出したバイト代は、すべてこれらの資金として消えていた。フォークギターは借り物、ステレオはおろか、レコードや音楽雑誌すらも買えない、悲惨な経済状況だった。
友人の部屋で加川良のアルバムを聴いた僕は、耳に残ったいくつかの曲をメモし、メロディはその場で覚えた。もっとも印象に残ったのが、「戦争しましょう」という曲で、ラジオでも一度も聴いたことがない。それもそのはず、いわゆる放送禁止歌なのだった。
逆説的に反戦をうたっており、歌詞は引用出来ないが、12番まであるとても長い琵琶歌のような構成の曲である。僕はその曲を何度も何度も聴き、完全に頭に叩き込んだ。
半年後の夏、寮祭のイベントで、中庭を使って20時間ぶっ通しのフォークライブをやるという。名づけて「僕たちの20時間」。出演者はすべて飛び入りだった。当時の僕はもちろんライブで歌った経験などない。しかし、それを体験する又とないチャンスがやってきた、と思った。
歌は加川良をやろうとすぐに決めた。ソロで歌えて、強いメッセージ性があり、喧噪の中でもある程度聴かせられ、しかも誰もがあまり耳にしない曲となると、「戦争しましょう」以外に考えられない。
ライブの1週間前から、猛烈に練習した。歌詞とコードを完全に覚える、いわゆる暗譜である。まともに歌うと10分近くかかるので、1曲でも充分そうだったが、予備として「悲しい気持ちで」を準備した。
「戦争しましょう」のコードは、そう難しくない。当時の僕はピックがなぜか苦手で、ストローク奏法だったのに、もっぱら爪だけで弾いていた。
いよいよライブ当日、同室の仲間(8人部屋の大世帯)や、サークルの友人には、すでに「やるぞ」と事前予告してある。ひそかにやるより、衆目の中で少しのプレッシャーがあったほうがより力を発揮出来る、過去の自分の経験から、そんな予感がしていた。
開演は夜7時ころだったが、曲目からして、夜が深まってから歌うのがふさわしい気がした。10時を過ぎると、どこからかわき出すように続々と人が集まってくる。飛び入りの順番待ちも行列状態で、仕切る人間もいず、じりじりと時が過ぎた。
夜11時ころ、強引にステージに上がった。スポットが当てられ、マイクも2本あって、本格的なライブである。観客は200人前後、中庭に入り切れない連中が、周囲の廊下にまで溢れていた。
自己紹介も曲目紹介も喋りも一切なしで、いきなり歌い始めた。はっきり覚えていないが、初めてのギターソロライブで、かなり舞い上がっていたのだと思う。
だが、ギターをジャーンとかき鳴らすと、妙に心が落着いた。観客は大勢いたが、あたりは漆黒の闇、赤いピンスポットを浴びて、一種の恍惚状態に陥ったのだと思う。
原曲を聴いていただくと分かるが、「戦争しましょう」は過激なタイトルの割には、本人の加川良は穏やかに抑制した感じで歌っている。しかし、僕が原曲を聴いたのは、ただの一回きり。しかも、半年の練習の中で、自分なりにかなり解釈を変えてしまっていた。僕がそのとき歌ったのは、カポでキーを原曲よりもかなり上げ、声をシャウトさせた激しい唱法だった。
しかし、その絶叫に近い唱法は、結果的にその場の雰囲気にピタリと収まった。中庭なので屋根はないが、囲むように高い木製の回廊に囲まれている。専門的なことはよく分からないが、音の抜けと反響のバランスが、実にいい感じだった。
12番まである物語調の曲なので、抑揚やリズム進行に気を配れば、徐々に観客を引きつけることが出来る。そんなステージと客席のつながり、駆け引きのようなものを、最初のライブであるこのとき、僕はすでにつかんでいた。歌いながら、闇の中で観客の熱い視線と心とが、自分にぴったりと寄り添ってくる、そんな確かな手ごたえを感じた。
曲が終ると、大きな拍手と歓声がしばらく鳴り止まなかった。僕はこの1曲だけで精魂を使い果たし、ステージを去った。準備していた2曲目を歌う必要はもはやなかった。ただ1曲だけで僕は充分に満ち足り、そして燃え尽きていた。

最初の野外ライブ「僕たちの20時間」/1972.6

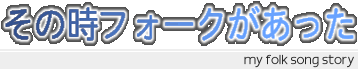


 菩提樹 /1962
菩提樹 /1962
 白いブランコ /1969
白いブランコ /1969
